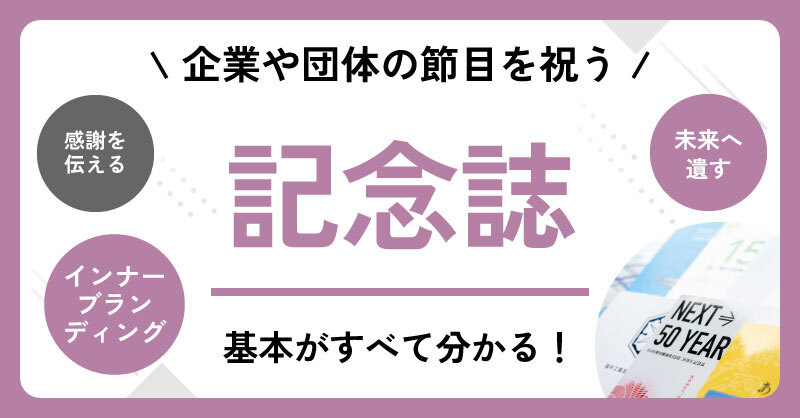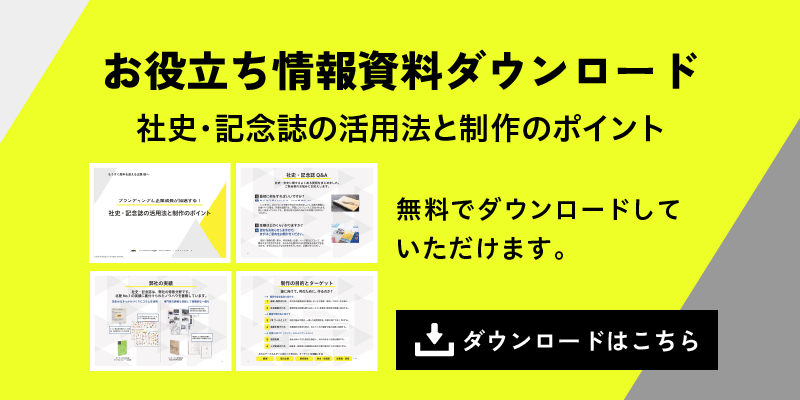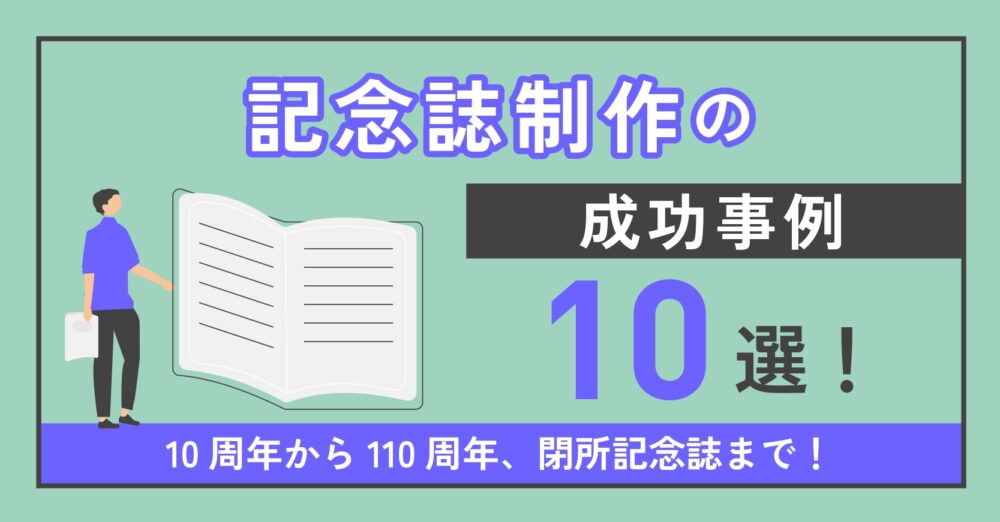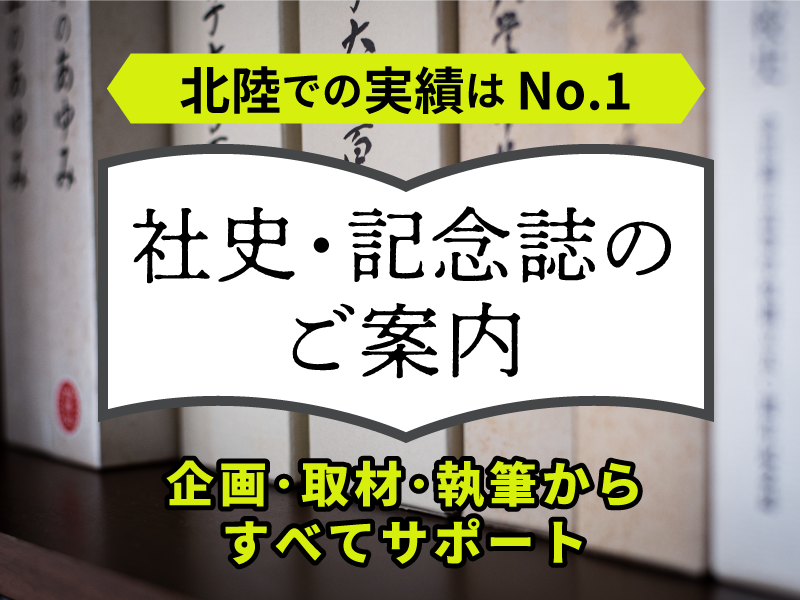記念誌制作における写真集めのコツとは?
- 2025年5月8日 (更新:2025年8月15日)
- 社史・記念誌
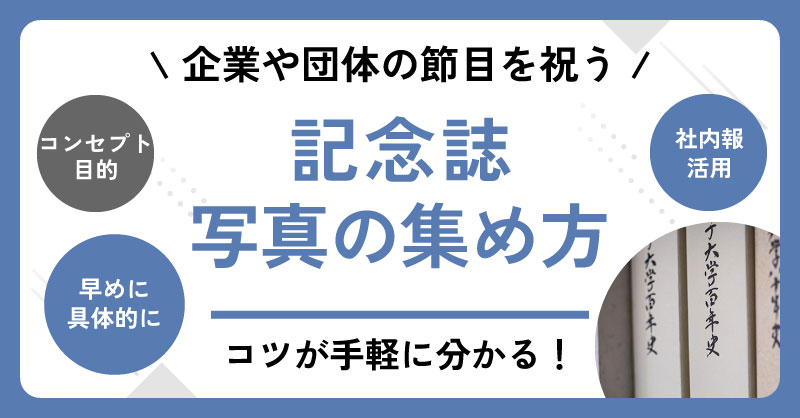
10周年や30周年など、企業創業や団体設立の節目の年に発行されることの多い記念誌。その記念誌制作において、さらに効率の良い進め方を知りたい、という担当者も多いはずです。そんな方に向けて、制作のコツをピックアップし解説します!
⬇︎記念誌全体についてはこちらで詳しく解説しています!
記念誌の写真の集め方
記念誌を作る上で欠かせないのが「写真」です。文章だけでは伝わりにくい空気感や、当時の雰囲気、人々の表情を鮮やかに蘇らせてくれます。ですが、いざ集めようとすると「どこから手をつければいいの?」「意外と集まらない…」と苦戦することも。今回は、記念誌制作で役立つ写真集めのコツをご紹介します。
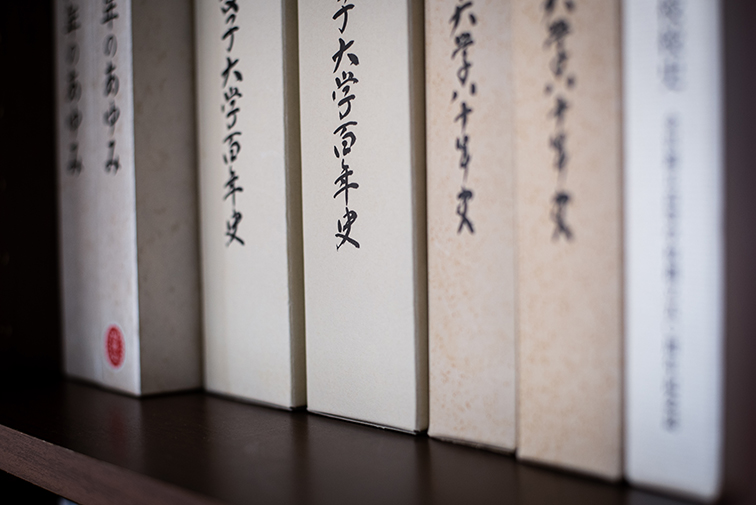
1. まずは担当者を決めて、編纂委員会を立ち上げる
スムーズに記念誌を進めるには、最初に「記念誌編纂委員会」を立ち上げ、役割分担を明確にすることが重要です。特に写真集めは、多くの人に協力を仰ぐ必要があるため、「写真担当」をあらかじめ決めておくと、情報の集約・管理が格段にラクになります。
編纂委員会では、次のような業務を主に行います。「誰が何をするのか」をはっきりさせておき、責任の所在を明確にしましょう。そうすることで、作業が滞りにくくなります。
-
全体の進行管理
-
写真収集・整理
-
原稿依頼・編集
-
デザイン・レイアウト
-
校正・印刷対応
2. コンセプトや目的を明確にしよう
記念誌づくりでもそうですが、写真集めにおいてもまず考えたいのが、「何のために作るのか」「どんな記念誌にしたいのか」というコンセプトや目的です。「創立○周年の歴史を振り返る記念誌か」「社員や関係者との思い出をつなぐ冊子なのか、次世代に伝えたいビジョンをまとめる資料なのか…」など、目的によって、収集すべき写真や掲載内容の方向性が大きく変わります。はじめにコンセプトを決めておくことで、写真集めがグッと進めやすくなります。
3. 早めの呼びかけがカギ
写真集めは「後でまとめて」が通用しない作業のひとつです。関係者が多ければ多いほど、やりとりにかける時間が必要になります。できるだけ早い段階で、「○月○日までに、○○に関する写真を送ってください」と具体的に呼びかけましょう。
4. テーマ別に募集すると集まりやすい
「何でもいいから送ってください」より、「○年の○○イベント」「研修の様子」など、テーマを絞って呼びかけると、記憶を辿りやすく、選定しやすくなります。時系列やカテゴリで募集テーマを小分けにして、数回に分けて呼びかけても良いでしょう。
5. 社内報を活用しよう
過去の社内報には、貴重な写真やエピソードがたくさん眠っていることが多いです。行事やイベントの様子、社内の人たちの表情、当時の出来事を知る資料としても役に立ちます。アーカイブが残っている場合は、ぜひ一度見直してみましょう。社内報の写真をスキャン・再使用する際には、解像度や使用許可の確認も忘れないようにしましょう。

6. デジタル・アナログ両方に対応
最近はスマホで撮った写真が主流ですが、昔の写真はプリント写真のみということも。デジタルデータはメールやクラウド共有、紙の写真は郵送や持参してもらう形など、どちらにも対応できる体制を整えておくと、より多くの写真が集まります。
7. 写真の説明・人物名も忘れずに
どんなに良い写真でも、「誰が写っているのか」「いつどこで撮られたのか」が不明だと、記念誌に使いにくくなります。写真を提供してもらう際は、簡単なキャプション(例:2000年研修発表会・○○社長と○○さん)も一緒に記入してもらえるように依頼しましょう。
8. 集まった写真は丁寧に整理
送られてきた写真は、日付・イベント別などでフォルダ分けして保存しましょう。後から「あの写真どこだっけ?」とならないよう、整理とバックアップも大切です。GoogleフォトやDropboxなどのクラウドサービスを活用するのもおすすめです。
弊社では記念誌の写真集めのサポートも承ります!
弊社・能登印刷(ナレッジクライマー)では、記念誌制作に重要な、煩雑な写真の取りまとめのサポートも承っています。コンセプトに合わせて、どんな画像が必要かなど、一から伴走して一緒に記念誌を作り上げることが可能です。
もちろん、それ以外にも制作進行、コンセプトの確定等のお手伝いも任せてください。弊社の編集部では、どんな情報をどんな方法で収集可能か、
⬇︎弊社の記念誌の制作事例はこちらからご覧いただけます。
▶ 弊社・ナレッジクライマー(能登印刷)の社史・記念誌制作サービスについて詳しくはコチラ
▶弊社・ナレッジクライマー(能登印刷)の周年記念サポートについて詳しくはコチラ

アーカイブ
- のとのお仕事 (41)
- 基本がわかる!シリーズ (20)
- 成功事例まとめ (8)